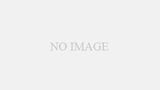コーヒーブレイク (こちらは、実際のニュースからヒントを得て、脚色したフィクションです。)
影のジャンヌ・ダルク
指令2 少女の存在を国際社会に気づかせよ
「これはボスからの案件ではない。某掲示板に直接訴えがあった。」
「場所は、イラン。16歳の少女が外出後、消息を断ち、後に遺体で発見された。」
「ふむ。」
「その遺体の状況から、家族は、殺害されたと訴えた。しかし、当局には取り合ってもらえず、国際社会もまだ、この事件に注目していない。」
「なるほど、それで、今回のミッションは?」
「リサーチの結果、彼女は、ヒジャブを巡って加熱している抗議デモに参加したあと、当局から逮捕、暴力の末、亡くなったと見られる。」
「まだ16歳だろ、むごい話だな、、、」
「今回のミッションは、国際社会に気づかせること。」
「作戦は?」
「彼女が注目されない要因は、同じようにして亡くなった第一被害者の女性をヒロインとして、各国メディア報道が加熱しすぎていることだ。」
「なるほど」「あほメディア」「ワンパターン」
「まずは、伯母の訴えの裏取りリサーチ、できた者からSNSへの投降。私は、Human Rights Watchとイランの有力女性政治家・活動家にコンタクトを取ってみるよ」
「了解」「幸運を」
脚光を浴びた第1ヒロイン
こちらは、『スカーフが招いた22歳女性「悲劇の死」・・・抗議デモが止まらない、イランが抱える「本質的な問題」宮田 律, 週刊現代(2022 10.17)を要約、引用したものです。
イラン北西部クルディスタンから首都テヘランに遊びにやってきたマフサー・アミニさん(22歳)は、宗教警察と呼ばれる指導パトロールに、スカーフの髪の隠し方が不十分だとして逮捕された。
ここまでは、あるかも知れない出来事だったが、その後、彼女が当局の暴力によって死亡したことが濃厚となった。
あるかも知れない出来事と書いたが、イランは昔から一貫して、スカーフや服装に関して、これほど厳しかったわけではない。
一説には、一時期は、欧米並みに自由な暮らしをしている女性もいたし、宗教色が強くなって以降も、指導はあくまで指導であって、強く注意する程度だったという。
当初、宗教警察は、アミニさんの死因を心不全と発表していた。
しかし、それが嘘だとわかると、彼女の生まれ故郷であるサッケズで抗議デモが発生し、瞬く間にイラン各地に波及していった。
イラン政府は、これらのデモの広がりに危機感を抱き、力と脅しによる弾圧を開始した。
発表によれば、4週間で民間人の犠牲者は分かっているだけで200人に達していた。
現在、イラン政府は、女性たちにヒジャブと呼ばれるスカーフとコウテ・イスラミーと呼ばれるコートの着用を義務づけている。
原則として、女性は髪と、体の首から膝下までを隠すことを要求される。
そのため、あえて、イスラムの伝統的なチャードルという布で手っ取り早く、すっぽり全身を隠す女性もいる。
また一方で、身を覆うこのような習慣に強い抵抗感を持つ女性たちも増えている。
かつて、イランにもパフラヴィー朝(1925〜1979年)という時代があり、世俗化政策が行われた時期もあった。
特に1936年1月に出されたベール着用禁止令(レザー・シャー初代国王)は、現在の状況からは想像できないだろう。
レザー国王は、「脱イスラム」を通して、かつてのイラン大帝国時代の栄光を取り戻そうと考えた。その甲斐あって、当時のイランの女性は、競うように欧米ファッションで着飾った。
(当時の様子が、高倉健主演の映画『ゴルゴ13』1973年、佐藤純弥監督で見られるというから面白い。)女性達にとって自由な時代が過ぎ去ったのは、1979年にイスラム指導者が革命の名の下、イスラム教回帰を強制したことに始まる。
これは国王の欧米化政策に、真っ向から対抗するクーデターのようなものだったのだろうか。当然、女性たちは、その年の3月8日の国際婦人デーを機に、大規模なデモが起こしたが、指導者は規制を緩めることなく、服装コードについて更に厳格な措置を採り、罰として公的機関への出入りを禁止するなどした。
1997年になってようやく、ハタミ政権(〜2005年)が改革を唱え、女性の服装の厳格化が少し和らぎ、イスラム・コートも短い丈が着られるまでになった。
同様に、ロウハニ政権(2013〜2021年)下でも、規制は緩めだった。このような行ったり来たりを繰り返しながら、2021年、保守強硬派ライシ大統領が誕生すると、また服装規制は「厳格」に後戻りした。
イランは、中東イスラム諸国の中では、女子学生が突出して多いと言われる。
『テヘラン・タイムズ』によれば、大学の半数以上が女子で、ある意味進んでいる国と言える。今回の抗議デモで大学が拠点になっているのは、そういった事情もあるようだ。
知識のある国際感覚を持った学生が、国政への不満を訴えることは、世界共通、時代時代で、先進国が目撃したきたことではないだろうか。
女子学生たちが望んでいたことは、先進国では当たり前の、女性の自由だった。
彼女たちの訴えを知った欧米の女性たちは、同じように髪を切ったり、スカーフを焼いたりして、彼女たちに共感と応援の意を表明し始めた。
こういう場合、その意義を読み間違えたり、過激な思想に突出してしまう集団や、流行として世論の波に安易に乗る人が現れるのも、よく起こる社会現象のようだ。
実際、ヒジャブそのものを蔑んだり、否定したりといった偏見へと発展させる者も現れ始めていた。 忘れてならないことは、イランの抗議デモは、スカーフが象徴として使われはしたが、突き詰めれば、権威主義的手法への反発だったということだ。
フランスなどの欧米では、イランとは真逆にスカーフなどのイスラムの装いそのものを禁止したり否定する動きが現れた。
ヨーロッパ諸国では、シリア内戦などでムスリム移民が増えたことを背景に、移民排そを唱える極右勢力が台頭し、イスラム女性へのヘイト・クライムが増えていた。米国では、2018年、トランプ第一政権で、イランに対する経済制裁が強化され、イラン経済は困難を極めるようになった。
イラン国内のインフレ率は60%、失業率は11%余りで、特に若年層にその皺寄せが降りかかっていたと言える。また、イランの少数民族クルド人の居住地域や、少数民族バルーチ人が住む南東部バルーチスタンでも同様だった。
イランでも他国同様に、少数民族は軽視されてきた歴史背景がある。
少数民族地域は、経済発展から取り残され、もともとの言語の使用を制限され、分離独立を恐れた政府によって、迫害されてきた。
亡くなったアミニもまた、少数民族クルド人の出身だった。
台の上でスカーフを掲げる後ろ姿の少女
(実際のニュースからヒントを得て、脚色したフィクションが含まれます。)
ニカは、スカーフデモに自分も参加しようと思った。
今まで鬱屈した気分で暮らしてきたので、こんなに心が高揚する気分は初めてだった。
変わることのない日々に諦めかけていたとき、突然世界が、イスラムの女性たちを英雄として認めてくれたようだった。
自分もあの場所に加わるのだ。
そう考えると、居ても立っても居られなくなり、同居する伯母さんに、出かけることだけを伝えて、夕方に家を出た。
デモが盛んな市内までは、少し距離があった。
伯母さんは心配して、1時間おきに電話をかけてきた。
そのたびに、「大丈夫、今日は友人の家に泊めてもらうから、明日には帰ります。」と答えたが、これといった当てがあったわけではなかった。
現場にたどり着くと、そこはもう、デモの群衆が通り過ぎたあとで、散らばった物と、布の焦げた臭いが広がっていた。
当初、女性ばかりと聞いていたデモは、その勇敢さに触発された男性たちにまで広がり、より一層の過激さを増していた。
棍棒を振りかざす当局は、そんな反逆者たちを容赦無く数人がかりで取り囲んでは殴打するなどしていた。
警察の力による市民への鎮圧は、当初、イランの春と称された盛り上がりに翳りを落とし始めていた。
神と称される最高指導者をも恐れなかった知識人やジャーナリストたちが、次々と居場所を割り出され拘束され、拷問をうけた。
連日、Twitterでは、今日は、誰々が拘束された、という暗いニュースばかりが目立つようになっていた。
ニカは、その日、押し倒された鉄のゴミ箱のような物の上に上ると、自分の持ってきたスカーフを高く掲げて、行き場を無くしたかのように彷徨く男達を鼓舞した。
その後ろ姿は、まるで、フランス革命に突如として現れたジャンヌ・ダルクのようで、偶然居合わせた海外ジャーナリストが、思わず彼女に向けてシャッターを切った。
彼女の伯母は、ただ心配性だったわけではない。
スカーフデモが盛り上がっていることは、ニカの友人から聞いていたし、家を出る前のニカの目が、いつもと違って、ある種の凛々しさを湛えていたからだ。
ニカの友人によれば、すでにニカは当局から目をつけられていると打ち明けていた。
自分のヒジャブを燃やす動画をインスタグラムに上げているからだと言っていたという。
夜の7時頃、伯母は胸騒ぎがして、ニカに電話をかけた。
電話に出たニカは、怯える声を押し殺すように、「治安部に見つかった。今、尾行されているから、あとでまた電話するね。」と言って電話を切った。
しかし、それが最後の会話になってしまった。
伯母は、彼女と連絡が取れないことを、近所や友人に訴えたが、警察は、まともに取り合ってくれず、誰もどうすることもできなかった。
そんな伯母の元へ、ニカのスマフォから電話があったのは、連絡が途絶えてから10日が過ぎたころだった。
伯母が急いで電話に出ると、相手はニカではなく、とげとげしく乱暴な男の声だった。伯母は何が起こったのか一瞬、頭が真っ白になったが、相手が警察であることを、しばらくして理解した。
拘置所の遺体安置所は、暗く、異様な臭いがして、目眩がした。
無造作にかけられたシートを警察官とおぼしき男が少しめくると、青ざめて目を閉じたニカの顔がそこにはあった。
伯母は、心臓が止まりそうになったが、倒れるのを必死で耐えて、姪のニカで間違いないと答えた。
男は、再びすぐに、シートを被せて、遺体は検死があるため、しばらく引き渡せないと言った。
無力感
「だめだ。まだ、アミニの話で持ちきりだ。」
「カウンセラー、そちらの首尾は?」
「ツイッターのダイレクトメールで、送ったから、そろそろ誰かが反応するんじゃないかな?」
「よし、しばらく様子をみよう」
翌日、Twitterでは、フォロワー数を誇るイランの女性政治家が、ニカの事件に言及したことで、またたくまにイラン国内を中心に拡散されていった。
新たな犠牲者が16歳の少女であったこと。性的暴行をうけていた可能性という憶測などから、更に今まで不明だった、拘束中の動画まで、さまざまな情報が拡散されるようになった。
「俺たちは、やり遂げたと思うか?」
「、、、」
「カウンセラー、なんとか言ってくれ」
「そうだね。やり遂げたとは言えないけど、立ち向かったとは言えるんじゃないかな」
「これからも続ける自信がなくなりそうだよ」
「自信?そんなの私たちに、始めからあったっけ?
内的動機、、、どうせ、この先も、動かずにはいられなくなる。ただそれだけだよ」
「そうだな」
「なあ、俺たちは、いったい何と闘っているんだろう?」
「そうだね、、、大きくて頑丈な壁に取り囲まれるのを阻止しようと、もがいてるんじゃないかな?
本能的に」
「その壁が、幸か不幸か、見える連中が、ここにいる。」
「一度は死にかけた奴らばかりだからな。」
「条件の二つ目、だね!」「おー!」「その通り!」
「おまえら、いつから、いた?」
「いや、ちょっと取り込み中のようだったから、静かに」「してました!」
「チーフの弱音を久しぶりに聞いたね、ふふふ」
「はい、解散!」
「了解!」「おー!」「またねー」「祈りの時間だわ」「お腹すいた」
「おまえらの、ノー天気には救われるよ(笑)」
世論で動くメディア
ニカは、尾行を撒くために、通りがかりに見つけた建築中と思わしき建物に一旦、入ってみた。
外からは工事がストップしているように見えたが、進んでいくと、警察官に雇われたとおぼしき男達がたむろしていた。
ニカは、何気ないふりをして、向こう側の出口まで、通り抜けると、そこから全力で走った。
以下は、「インスタで抗議の16歳少女、遺体で発見 当局は8人逮捕 イラン」 CNN World (2022.10.6)の記事を引用、要約しています。
タスニム通信によると、逮捕された8人は、シャクラミ(ニカ)さんが入ったとされる建物で働いていた。
また、ファルス通信は、警察と司法機関から入手したという映像を公開していた。
そこには、歩いて路地から家の中に入る人物が映っており、マスクをおろした表情は鮮明ではないが、それがシャクラミさんであるという。その映像の7時間後に遺体が発見されたと当局は説明したと伝えた。
国営イラン通信は、テヘランの検察が、この事件の捜査を担当しており、シャクラミさんの遺族に哀悼の意を表した。
当局によって暴行された、という推測の拡散を止めるかのように、警察は、しばらくして容疑者が逮捕されたと報じた。
しかし、その真相はわかっていない。