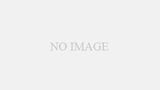コーヒーブレイク (こちらは、実際のニュースからヒントを得て、脚色したフィクションです。)
日本は夢の国?
以下は、ベトナムトレーディングの「日本での実習生の問題」
を参考に脚色したフィクションです。
夢を叶えるために日本へ
ベトナムの田舎町でタクシーの運転手をしているロックは30歳。
両親と妻、そして可愛い一人娘の家族5人暮らし。
懸命に働き、慎ましいながらも、平和に暮らしていた。
タクシー運転手の仕事は、月平均日本円で1万6千円ほど。ベトナムの平均月収と言われる金額からは1万円ほど少なかった。
久しぶりに休みを取った日、学校の友人の話をする娘に耳を傾けながら、家族が、この先ベトナムという国の中で、誇りを持って生きていくためには、どうすれば良いのだろう?この先、この貧しい暮らしから抜け出す日が来るのだろうか?と30歳のロックは考え始めていた。
そんなある日、たまたま乗せたお客と世間話をしていた。
子どもの学費の話になったとき、恰幅のいい客の男は、
「最近は、日本に出稼ぎに行く男が増えている。」
「なんでも、月給10万くらいは普通に稼げるらしい。」と話した。
尋ねると、心当たりの仲介者の電話番号を教えてくれた。
ロックは、詳しく話を聞くために、さっそく次の休日、その仲介者へ電話をかけてみた。
トントン拍子に、会って説明してくれるというので、約束の日、意気揚々と会社を訪ねて行った。
こ綺麗な事務所のソファーへ、慣れた様子でロックを案内すると、仲介会社の女性担当者は
「給料は月給で20万円から、頑張れば30万円も可能です。」
「基本的に労働時間は8時間で、週2日は休みとなっています。」
「住まいは、実習先の会社が用意してくれる寮があります。」と丁寧な口調で、パンフレットを指し示しながら説明をした。
ロックは、急に舞い込んだ幸運に、気分が高揚した。
日本という国は素晴らしく進んでいると、タクシーのお客から噂には聞いたことがあった。
けれど、そこまで条件が良いなどとは予想だにしていなかった。
「日本だからきっと、それが可能なのだろう。素晴らしすぎる。」
しかし、本契約の段階になって、少し気がかりなこともなかったわけではない。
仲介会社が、渡航の条件として、日本円にして150万円の前払いを提示してきたからだ。
ロックにとって約8年分の給料に相当するそんな大金が出せるはずもなく、内心、諦めかけた頃、仲介会社の男は、「あまり、人には言えないけれど、どうしても日本へ行きたいなら、お金を貸せる」と言ってきたのだった。
「こんな機会は、人生でもう2度とないだろう」ロックはそう心を決めて、口外しないことを条件に、その裏技に乗ることにした。
それは、信用のためと称する、家と土地の権利書を仲介会社に提出することだった。
契約当日、書類へのサインとの引き換えに、権利書は戻ってきたので、ロックはさほど深くは考えないことにした。
「日本に行きさえすれば、人生が変わるに違いない。これは、そのための一生に一度の投資なのだ。」 「今まで通り、まじめに働きさえすれば、ベトナムとは比べ物にならないくらい稼げるのだから、家や土地が取られることは、きっとないはずだ。」
ロックは、日本という国に自分と家族の夢をかけて、2013年3月、「農業技能実習生」という肩書きを手に日本へ旅立った。
消えたヤギ
「先生、毒草、今日も異常なしです。」
「よーし、水仙は毒性あるから、綺麗でも除去してくれよ」
「わかりました」「了解です」
京都大学大学院では、空き地の雑草地を利用して、都市域におけるヤギを利用した緑地管理方法の研究を行っていた。
研究は、他の大学の成果を参考に、去年の春から立ち上げられたものだ。
当初は、近隣住民からの、臭いや鳴き声などによる苦情が予想されていたが、掲示板へのポスターによる概要説明など、抜かりなく行ったため、今のところ苦情や問題は起こっておらず、データは順調に記録・蓄積されてきた。
「あのポスターが効きましたね」
「最近は、複数の才能を持つことがトレンドらしいな」
「二刀流ですね」
「すぐ、調子にのるところは、俺たちの頃と変わっていないが」
(笑い)
「先生、もう1年になりますし、今年は近隣住民とのイベントなんかどうでしょう?」
「そうだな、お前たちに任せるから、企画ができたら見せてくれ。但し、あくまでデータ研究が優先だぞ」
「わかってます!」「ちょっと楽しそう」
そんな和やかな雰囲気の中、教授のスマホがポケットの中で、大きな音をたてた。
「なんだって?!」「おいおい、まじか」
「先生、どうしました?」
「みんなは、ルーティンを怠りなく続けてくれ」「草地Bのヤギが2匹共いなくなった」
「行ってくるから、吉田、あと頼む」
「はい、後で報告します。」
(ざわざわ)「B班、終わったか、、、、」「まさか、どこかの畑、荒らしてないよな?」
(ざわざわ)
参考
『都市域における山羊を利用した緑地管理活動の研究』曽根, 山田, 山本, ランドスケープ研究 75(5), 2012
日本語教室
「先生、お久しぶりです。」
「はい、お元気でしたか?」
「ええ、なんとか。先生の方はいかがですか?」
「相変わらずです。ベトナム人留学生は、色々大変です、、、」
「あぁ前にも 仰ってましたね。ポップアイドルに夢中になって、大学辞めたとか、冬にエアコンの温度を汗が出るほど上げたままにしてるとか、、、」
「それぐらいならまだ良かったのですが、、、」
「何かありました?」
「実は、生徒が一人、行方不明になりまして、、、」
「それは、穏やかではないですね」
「まぁ、しばらくして、警察に保護されたんですが、理由を聞いて、複雑な気分になってしまって」
「はあ、、、、理由は何だったんですか?」
「平たく言えば、アルバイト先で少し、トラブルがあって、何もかも嫌になってしまったようなんです。」
「違う文化で、日本語がまだ得意でないうちは、コミュニケーションも行き違いがあったりするでしょうね。特にベトナム人だと、日本人特有の空気を読む習慣には不慣れでしょうし」
「そうなんです。彼らは、大金を払って留学して、アルバイトをせざるを得ないようなんですが、コンビニなどは、人手不足なのか、シフトを勝手に変えられたり増やされがちで」
「はっきり言ってブラックですよね」
「ええ、店舗にもよるとは思うのですが、アルバイトの出入りが激しいところは、止めておきなさいとしかアドバイスできない状態で。」
「彼の場合も、大学生だから、これ以上、シフトを増やさないでほしいって身振り手振りで訴えたらしいのですが、それを日本人の同僚や先輩に反抗的って取られてしまったみたいです。」
「それで行方不明に?」
「結局、そのいざこざがあった夜、仕事がなくなったことがショックで、寮には帰らず、街をぶらついていたらしいんです。」
「まぁ、気持ちは分からないではあります。」
「あなたなら、そう言うと思ってました。」
2013年頃、ベトナム人留学生に特徴的な問題として、以下のような点が業界では指摘されていた。
経済的な問題:
高額な家賃: 特に都市部では家賃が高く、経済的に苦しい留学生にとって大きな負担となり、複数人で一部屋に住むなど、住居環境が劣悪になるケースも見られた。
留学費用の借金: 日本への留学費用を工面するために、母国で高額な借金をしてくる学生が少なくなかった。そのため、来日直後から経済的なプレッシャーにさらされ、学業に集中できないこともあった。
生活費・学費のためのアルバイト: 物価の高い日本での生活費や学費を稼ぐために、長時間アルバイトをせざるを得ない学生が多くいた。過度なアルバイトは、睡眠不足や学習時間の不足につながり、学業不振の原因となっていた。
学習面の問題:
- 日本語の習得の困難さ:
- 漢字の習得: ベトナムでは漢字を使用しないため、多くの漢字を覚えることに苦労する者が多い。
- 文法や表現の違い: 日本語の文法や表現が母語と大きく異なるため、理解に時間がかかることがある。
- 発音: 日本語とベトナム語の発音体系の違いから、発音に苦労する。
- 学習習慣の違い: 日本の教育システムや学習方法に慣れるまでに時間がかかることがある。例えば、予習・復習の習慣がない、積極的な質問をすることに抵抗があるなど。
- モチベーションの維持: 経済的な困窮や学業の遅れから、学習意欲が低下してしまうことがあった。
文化・生活習慣の問題:
- 日本独特の習慣への不慣れ: ゴミの分別、公共交通機関の利用、近隣への配慮など、日本特有の生活習慣に戸惑うことがある。
- コミュニケーションの難しさ: 日本人とのコミュニケーションに不安を感じたり、文化的な違いから誤解が生じたりすることがある。
- 孤立感: ホームシックや文化的な孤立感から、精神的に不安定になることがある。
その他の問題:
在留資格の問題: 学業不振やアルバイトの問題などが原因で、在留資格の更新が難しくなる者がいた。
悪質な仲介業者の存在: 一部の悪質な留学仲介業者が、不当な手数料を請求したり、実際とは異なる情報を提供したりするケースが確認された。
*以上、AIアシスタントGeminiの回答を利用
これらの問題は、ベトナム人留学生全体に当てはまるわけではありませんが、他の国からの留学生と比較して多く見られる傾向があります。日本語学校や大学は、これらの問題に対応するために、様々なサポート体制を整えることが求められています。
鳴り物入りの海外派遣日本語パートナー事業
「そういえば、あなたは、てっきり日本語パートナーズでまた海外へ行くものとばかり思っていました。」
「田中先生に推薦書も書いて頂いたのに、一時審査で落ちてしまいました。」
「あぁ、そうだったのですね。悪いことを聞いてしまいました。」
「いいんです。自分に実力がなかっただけですから」
「実力ですか、、、応募者が多かったのではないでしょうか?」
「ええ、そう思うことにします。ありがとうございます。でも、おかげで、遅まきながら心理学で学士も取れましたし、大学院生の気分も味わうことが出来ましたので、人間万事塞翁が馬です。」
「はは、あなたらしい。でも、大学院も行かれたとは、知りませんでした。ひょっとして、それも通信ですか?」
「ええ、そうです。」
「私には、とても真似ができません。試験がない分、通学生の何倍もレポートが必要で、ズルもできないと聞いたことがあります。」
「いえ、試験はWebでありますし、卒業研究もあります。受けられないのは、正規の実験実習や論文指導くらいです。」
「努力家なんですね」
「いえ、若い頃、サボってた反動ってだけですよ。先生のように優秀で、有名大学に現役で合格して、奨学生になるなんて尊敬しかないです。」
「奨学生になどなるものじゃないです。全額返済できたのが、50歳ですからね(笑)」
日本語パートナーズ政策は、2013年12月に東京で開催されたASEAN特別首脳会議において、日本政府が発表した新たなアジア文化交流政策だった。
このプロジェクトは、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年を目標に、東南アジアを中心としたアジア諸国と日本との文化交流を抜本的に強化することを目的としており、その柱の一つが「日本語学習支援」だった。
具体的には、国際交流基金アジアセンターが中心となり、2014年度から、アジアの中学校・高校などに日本人を「日本語パートナーズ」として派遣する事業が開始された。日本語パートナーズは、現地の日本語教師や生徒たちのパートナーとして、日本語授業のアシスタントや日本文化の紹介などを通じて、日本語教育と国際交流に貢献することを目的としていた。
当初は、2020年までに3000人以上の日本語パートナーズを派遣することが目標とされていたが、2023年度までにその目標は一応、達成している。
日本語パートナーズ派遣事業は、単に日本語や日本文化を一方的に伝えるだけでなく、派遣された人も現地の言葉や文化を学び、相互理解を深める双方向の交流を目指していた。また、幅広い世代や経歴を持つ人々が参加できる門戸の広い事業と謳っていた。
その後、日本語パートナーズ事業は、多く採用された人々にとって、貴重な経験となっている一方で、いくつかの問題や課題が指摘された。大規模な事件というよりは、個々の派遣や制度運営に関わるものとして、以下のような問題があった。
派遣されたパートナーからの報告に見られる問題点:
- 言語の壁: 現地語の習得が十分でない場合、コミュニケーションに苦労することがあった。特に、カウンターパートの教員や生徒との意思疎通、日常生活での情報収集などで困難を感じるケースがあった。
- 文化的な違い・カルチャーショック: 日本とは異なる習慣や価値観に戸惑い、ストレスを感じることがあった。食事、生活習慣、人間関係など、多岐にわたる場面でカルチャーショックを経験する可能性があった。
- 教育現場での役割の曖昧さ: 事前の説明と異なり、派遣先の学校で期待される役割が明確でなかったり、日本語教師のサポート以上の業務を任されたりする場合があった。
- 孤立感・ホームシック: 長期にわたる海外生活で、精神的な負担を感じることがあった。特に、周囲に日本語を話せる人が少ない環境では、孤立感を抱きやすい傾向があった。
- 住居・生活環境: 派遣先の住居の質や生活インフラが十分でない場合があった。衛生面や安全面で不安を感じるケースも報告されている。
- 健康管理: 海外での医療事情や衛生環境の違いから、体調を崩しやすい場合があった。
制度運営上の課題:
- 派遣前研修の充実度: 派遣前の研修内容や期間が、派遣先での活動や生活に必要な知識やスキルを十分にカバーできていないという意見があった。
- 派遣後のサポート体制: 派遣期間中の相談窓口やサポート体制が十分でないと感じるパートナーがいた。
- 情報共有の不足: 派遣先や活動内容に関する情報が、派遣者間で十分に共有されていない場合があった。
その他:
- 新型コロナウイルス感染症の影響: 感染症の流行により、派遣期間の短縮や派遣中止などの影響が出た。
これらの問題に対して、国際交流基金アジアセンターは、派遣前研修の改善、現地でのサポート体制の強化、経験者からの情報共有の促進など、様々な対策を講じていると回答している。
「しつこいようですが、私には、あなたがなぜ、書類審査で落とされたか分からないですね。半年とはいえムスリムでのホームステイや海外経験もあるのに」
「心当たりが、ないこともないのです。」
「なんですか?」
「抱負のところに、SNSで広く情報発信し、異文化についての理解を共有するって書いてしまったんです」
「それがどうして、ダメなんですか?」
「、、、笑。どうも、都合が悪いようなんです。」
「は?、、、」
制度の失敗
2024年6月14日、技能実習制度に代わる新たな外国人雇用制度「育成就労制度」を創設するための関連法改正が国会で可決・成立した。
技能実習制度の現状と課題
技能実習制度は、開発途上国への技能移転による国際貢献を目的として1993年に創設された。しかし、実際には労働力不足を補う手段として利用されるケースが多く、以下のような問題点が指摘されてきた。
- 低賃金・残業代未払い: 最低賃金以下の賃金や、残業代が支払われないケース。
- 長時間労働: 法定労働時間を超える長時間労働が常態化。
- 劣悪な労働環境: 安全配慮義務を怠るなど、劣悪な環境で労働を強いられるケース。
- 人権侵害・ハラスメント: 暴力や暴言、差別的な扱いなど、人権侵害やハラスメントの報告。
- 失踪: 低賃金や過酷な労働条件に耐えかねて、技能実習生が失踪するケースが後を絶たない。
- 目的と実態の乖離: 国際貢献という目的とは異なり、労働力確保が主な目的となっている現状から、国際社会の評価は厳しい。
新たな制度「育成就労制度」
このような技能実習制度の問題点を踏まえ、政府は新たな外国人雇用制度「育成就労制度」を創設した。この制度は、外国人材の育成と確保を目的としており、以下の点が技能実習制度から変わるとされている。
- 育成期間: 3年間の育成期間を経て、特定技能1号の水準に達することを目標とする。
- 転籍: 一定の条件を満たせば、転籍を可能とする。
- 対象分野: 現在の技能実習制度の職種を機械的に引き継ぐのではなく、特定技能制度における特定産業分野に限られる方向で検討。
- 日本語教育: 外国人の日本語教育支援は、強化される見込み。
移行スケジュール
育成就労制度への移行は、改正法の公布後3年以内に行われる予定で、2027年頃に本格的に開始されると見込まれている。制度移行後も3年程度の移行期間が設けられ、技能実習制度と育成就労制度が並行して運用される可能性も否めない。
以上、一部、詳細は、AIアシスタントGeminiの回答によるものです。